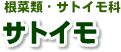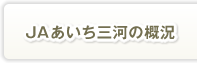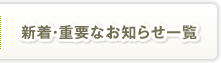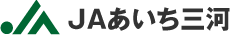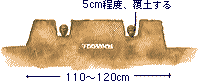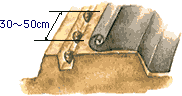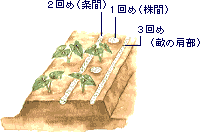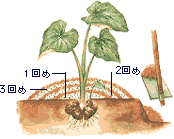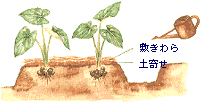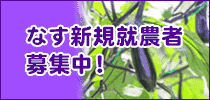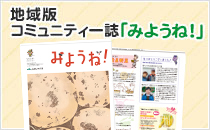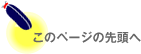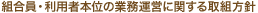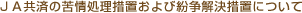| |
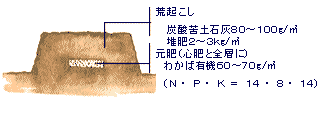 |
根が1mくらいにも伸びるので、深めに耕しておく。 |
|
 |
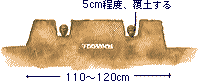 |
種イモは溝の中へ芽を上にして植える。
70~90cmの畝のばあいは1条植えにする |
|
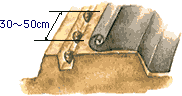 |
植えつけ後、黒色のポリマルチをすると、発芽が早まり、雑草も防げる |
|
 |
芽がマルチを突き上げてくるので、その部分を切って芽を外に出す。生育初期に太い芽を残し、他の芽は種イモを引き上げないように横に引いて取り除く。
|
|
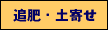 |
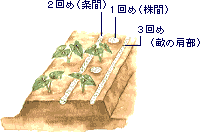 |
本葉2~3枚ころ1回め、本葉5~6枚ころ2回め、7月中旬に3回めの追肥、わかば有機40~50g/m2を施す。一度に多量に施すと肥あたりするので、こまめに少量ずつ施す。
|
|
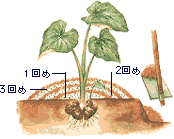 |
追肥と同時に土寄せする |
|
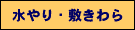 |
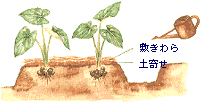 |
7月ごろから子イモが大きくなりはじめる。わらや枯れ草で乾燥を防ぎ、乾燥するときは畝間に水をやる。霜が降りる前に収穫する
|
|
|
|
|
ズイキ(サトイモの茎)や親イモを食べると、舌や食道粘膜が刺激されてえぐみを感じたり、人によってはイモの汁が肌に触れるとかゆくなったりかぶれたりすることがあります。こんなとき、焚き火などでかゆいところを暖めると、かゆみが止まります。
このえぐみ成分は、葉柄が緑色のものに多く、日照りが強く、乾燥したときに増加します。
軟白栽培した芽イモは日光を当てないので、えぐいイモを利用してもえぐみはでないのです。
えぐみは熱や酸によって分解されるほか、葉柄の皮をむいたり乾燥しただけでえぐみがなくなるほか、えぐいイモでも貯蔵しておいて春に食べるとえぐみはほとんどなくなっています。
|

|
|