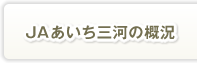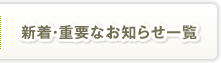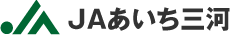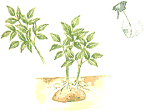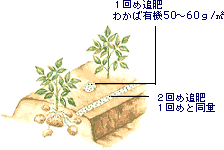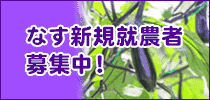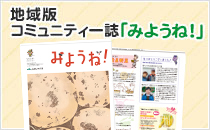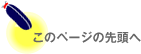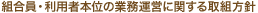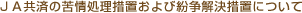家庭菜園
 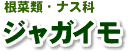 |
||||
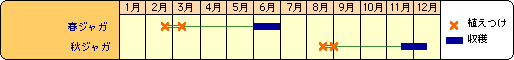
|
||||
VARIETY |
||||
|
||||
PROFILE |
||||
南アメリカが原産で、生育適温は15~24℃。17℃前後で塊茎(イモ)を形成し、30℃以上になると塊茎が形成されなくなります。霜に弱く、早植えして晩霜にあうと地上部が枯れてしまいます。
イモは収穫後、一定期間休眠します。一般に早生品種は長く、男爵で90日、紅丸やメークインは60日程度とされています。収穫後長期間だった種イモだと、育ちの悪い小型のイモが多数できてしまいます。そこで、作型によって適切な種イモを用意する必要があります。一般平坦地の春植えでは北海道産の種イモ、秋植えには長崎近辺の種イモが適当といわれます。
|
||||
|
||
|
||
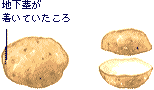
卵大のイモ60~90gなら二つ切りにする。頂部に芽が集中しているので、各片に芽を着けて切る。
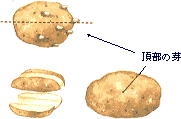
大きいイモ100g以上は縦に四つ切り。どの切片にも頂部近くの芽がついているように。切った種イモは2~3日、日に当てて緑化、切り口を乾燥させると早く芽が出る
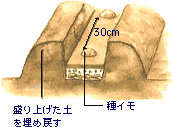
種イモは切り口を下にして並べる
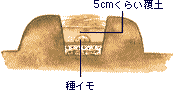
5cmくらい覆土し、切りわら、枯れ草を敷く
|
||
|
||

茎葉が黄色くなってきたころ、晴れた日に収穫する。
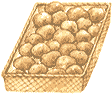
収穫したイモは日陰で積み上げないようにして乾かしておく。
|
|